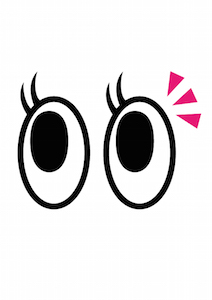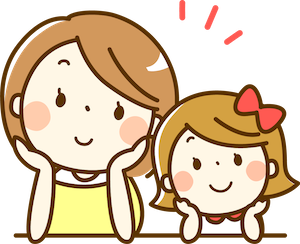アセスメント(機能分析)STEP1
特定の環境変化や行動(A)が引き起こす結果(B)が一貫している場合、AとBの間には「随伴性」(一方が起こると他方も起こる関係)が存在します。この随伴性を理解することで、それに対する対策を策定し、不適切な行動を改善することが可能になります。
A(環境の変化や行動)が起きると、必ずBが起きるという時、AとBの間には随伴性(付随関係)があるといえます。
随伴性を特定できれば、それに対してどんな事ができるか検討し、対策を打つことで望ましくない行動(問題)を改善することができます。
STEP1:付随関係(強化随伴性)を特定
行動は特定の役割(機能)を果たします。その役割が果たされることで行動が強化され、習慣化します。したがって、不適切な行動を減らすためには、その行動がどのような役割を果たし、なぜその行動が強化されて習慣化されているのかを理解する必要があります。
強化随伴性を特定するためには、観察が重要です。対象となる行動(ターゲット行動)を明確に定義し、その行動について観察を開始します。ただし、ターゲット行動の定義にはある程度の範囲を設けることが必要です。(反応クラスター=反応のある程度の範囲)

まず、行動が起こる状況を特定します。さまざまな状況を設定し、その範囲に該当する行動を一定時間観察しカウントします。行動が頻繁に起こる状況を特定したら、次にターゲット行動が起こる直前の刺激や環境変化、そして行動後の変化を記録します。
ただし、感覚的な強化(快感や不快感の増減)は個人の内面で起こるため、他人の行動を観察する場合には外部から確認することができません。また、自分自身の場合でも、これらの感覚はあまりにも当たり前のため、意識することが難しい場合もあります。場合も少なくありません。
何に対して不快感を感じ、何に対して快感を感じるかは個々に大きく異なります。他人の行動を観察する場合は、コミュニケーションを丁寧に取りながら進めます。自分自身の場合は、感情や体の感覚の変化に意識を向けて確認しながら進めましょう。